今日は2025年10月28日の日経電子版から、日米関係に関する記事を取り上げたいと思います。

記事の要約
来日中のラトニック米商務長官は、日本経済新聞の単独インタビューで、日米間で合意された5500億ドル(約80兆円)の対米投融資枠について詳細を明らかにしました。
この資金は主に電力やパイプラインなどリスクの低いインフラ事業に充てられ、日本企業10〜12社が既に対米投資を検討しており、年内にも第1号案件が決定する見通しだといいます。
中でも特に焦点となるのは、
- 米国の電力分野(ガスタービン供給など)への投資
- アラスカ州でのLNG(液化天然ガス)開発プロジェクト
であり、日本企業の技術力が米国のエネルギー供給拡大に活かされる形になります。
また、米商務省が投資関連の就労ビザ発給を緩和する方針を示し、従来の制度上のハードルを下げる姿勢を取った点も注目されています。
さらに、半導体や医薬品分野では、日米間で分野別関税を15%に据え置く合意を明文化する方向で調整が進んでいるといいます。
記事に至る経緯

2025年は、トランプ政権復帰後の通商政策再編の年でもあり、
米国は国内製造業の回帰とエネルギー自立を強化するため、同盟国との投資協力を重視する姿勢を鮮明にしているところです。
その中で日本は、インフラ・エネルギー・先端産業といった分野で米国との関係を深めることで、経済安全保障上のパートナーシップを強化しようとしています。
特に半導体やエネルギー分野では、サプライチェーンの安定が国益と直結するため、日米間の協調が不可欠となります。
また、トランプ政権下では保護主義的な政策が進む中、日本企業の米国進出にはビザ問題や関税リスクといった課題がありました。
今回の発言は、そうした懸念を和らげる実務的な保証のメッセージとしても位置づけられると考えられます。
見解
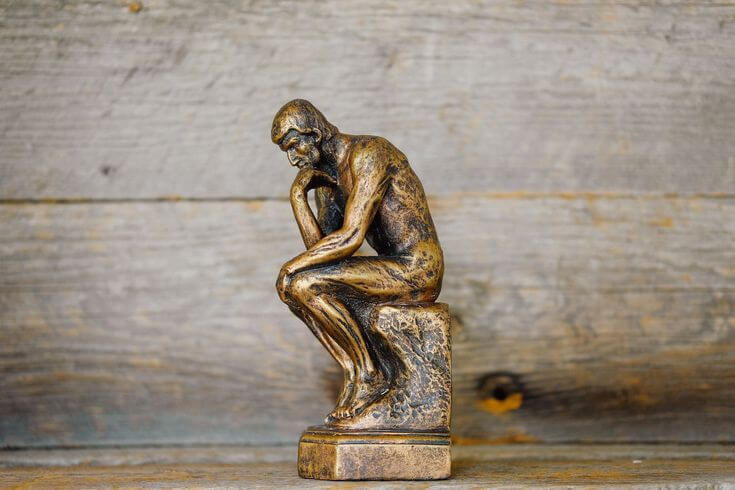
今回の発表は、単に投資の枠組みではなく、「経済安全保障のための協調投資」としての性格が強でしょう。
特に、エネルギー分野の投資を通じて日本がLNGの引取権を得る可能性は、エネルギー調達の多様化と安定化に大きな意味を持ちます。
一方で、懸念すべきはこの枠組みが「米国の国内政策の延長線」である点です。
日本側の資金や技術が米国の産業基盤強化に活用されることで、対等な関係が保たれるかどうかは今後の運用次第になります。
しかし、米商務省が就労ビザ発給に関与するという制度的柔軟さは、日系企業の参入を後押しする可能性があります。
従来の「保護主義一辺倒」とは異なる、「選択的な開放」の兆しとも言えると思います。
また、分野別関税で日本製の半導体・医薬品を優遇する姿勢は、米国にとってもサプライチェーンの信頼性を確保する現実的判断でしょう。
ここには、「敵対する国には制限を、信頼できる国とは共栄を」という新しい米国の通商スタンスが見て取れます。
まとめ
ラトニック米商務長官の発言は、日米経済関係の「再接続」を象徴していると言えます。
エネルギー・半導体といった国家基盤に関わる分野で、日本が資金と技術で支え、米国が制度面で支援するという新しい協調モデルが形成されつつあります。
一方で、日本側がこの投資を経済安全保障の観点からどう活かすかが重要です。
単なる資金提供に終わらせず、技術・供給・人材の循環を戦略的に確立できるかが、今後の課題となると考えます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=21692026&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0657%2F9784788720657_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=23767741&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2355%2F2000015542355.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント