先日書いた記事では日本政府による財政拡張によって円安が進む趣旨の内容を書きました。
そこではスルーしたけど、「そもそもなぜ財政拡張で円安が進むの?」と疑問が湧いてくるかと思います。
そこで、財政拡張と為替の関係性について
- 金融経済の基本としてのメカニズム
- 例外的な日本に特有の関係性
という項目に分けて、基本的な考え方から日本におけるレアケースの関係性を仮設してみたいと思います。
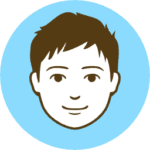
ガク
メカニズムというのは基本的な仕組みがある中でも、現実の状況によってさまざまな例外が生じるものです。
今回の話題ではまさに日本国内の特徴的な状況が例外を生んでいます。まずは基本を押さえて、なぜ日本が例外なのかを根本的に理解してしまいましょう!
金融経済の基本としてのメカニズム
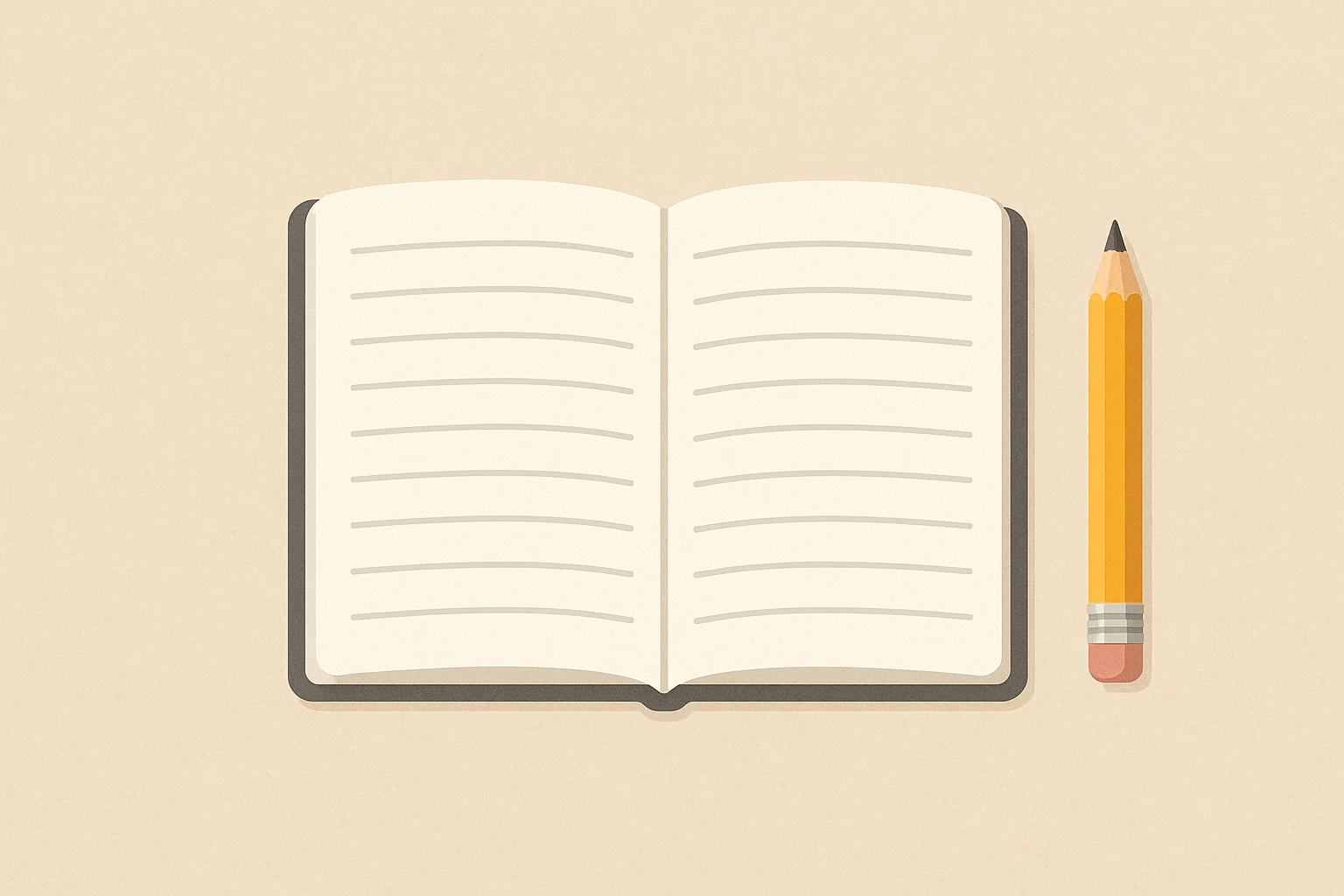
まず、一般的に「財政拡張(=政府支出の増加や減税などによる景気刺激策)」が為替に与える影響について見てみましょう。
財政拡張は多くの場合、政府が国債を発行して資金を調達し、その資金を公共事業や社会保障、補助金などの支出に回すことで実現されます。すると以下のような流れが起こります。
- 国債発行による金利上昇圧力
国債が大量に発行されると、市場に供給される債券の量が増えます。投資家に買ってもらうためには、相対的に金利が上昇しやすくなります。 - 金利差と通貨価値
通常であれば、金利が上がれば「その国の通貨で運用したい」という需要が高まり、通貨高(円高)が起こるのが理論的なメカニズムです。アメリカでは財政拡張=ドル高に結びつきやすい傾向があります。 - インフレ期待の上昇と通貨安
一方で、財政拡張はインフレを招きやすい政策でもあります。通貨の購買力が下がるという見方が強まれば、むしろ通貨安(円安)に働くこともあります。
つまり、理論的には「金利上昇 → 通貨高」と「インフレ懸念 → 通貨安」という2つの力が拮抗するのが通常の仕組みです。
例外的な日本に特有の関係性

では、なぜ日本では財政拡張が円安につながりやすいのでしょうか。これはいくつかの要因が重なった「日本特有のケース」と言えます。
- 日本銀行の金融緩和姿勢
政府が国債を発行しても、日銀が積極的に買い入れるため、市場で金利が上がりにくいという特徴があります。結果として「財政拡張しても金利は上がらない」構図が生まれます。 - 金利差の拡大による円安
アメリカや欧州がインフレ対応で利上げを進める一方、日本は超低金利を維持しています。このため、財政拡張で景気刺激をしても、日本の金利がほとんど動かず、相対的に金利差が拡大し、円安が進むのです。 - 投資家の信認と財政リスク
国債残高が大きく増えると「将来の財政は持続可能なのか?」という不安が強まり、海外投資家が円を売る動きにつながることもあります。この心理的な要因も円安圧力となり得ます。
まとめ
本来であれば「財政拡張=金利上昇=円高」という教科書的な流れになるはずですが、日本の場合は
- 日銀の大規模緩和で金利が抑え込まれる
- 他国との金利差が拡大する
- 財政リスク懸念が円売りを誘発する
といった特殊な事情が絡み合い、むしろ円安が進みやすい構造になっています。
つまり、日本では「財政拡張=円安」という逆転現象が起こっているのです。
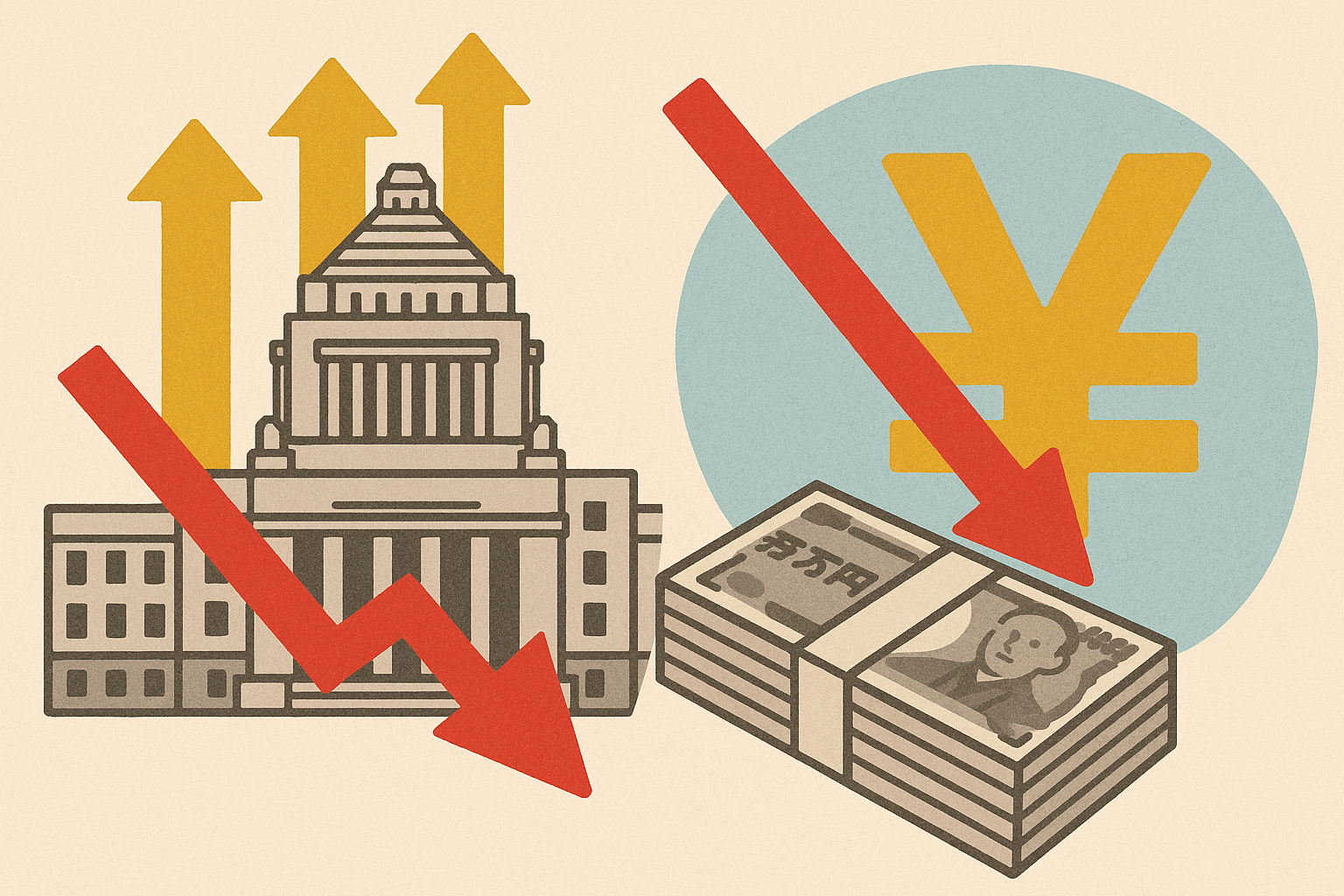
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=21711783&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0823%2F2000012120823.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=21168913&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9158%2F2000011159158.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=21135025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3867%2F9784322143867_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=21557367&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5038%2F9784322145038_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント