今日は2025年10月27日の日経電子版から、高市新政権に関する記事を取り上げたいと思います。

記事の要約
日本経済新聞の世論調査で、高市内閣の支持率が74%と高水準でスタートしました。この支持率を背景に、高市首相は安全保障政策の前進に力を入れています。特に、防衛装備品の輸出を制限している「5類型」の撤廃を目指し、防衛装備移転三原則の運用緩和に動き始めました。これにより、防衛産業の販路拡大や生産基盤維持を促す狙いがあります。一方で、安保政策の推進には野党との関係性や政権運営全体への影響など不透明な課題も残っています。
記事に至る経緯

これまで日本では、平和国家としての立場を重視し、殺傷能力のある武器の輸出には慎重な姿勢を取ってきました。「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5目的以外の装備品は輸出できず、ミサイルや護衛艦といった装備は共同開発国に限られていました。その背景には、公明党の反対による政策制約がありました。しかし、公明党が連立から離脱し、日本維新の会が自民党に協力姿勢を見せたことで状況が変化。5類型の撤廃が一気に現実味を帯びてきたタイミングでの報道と言えます。
見解
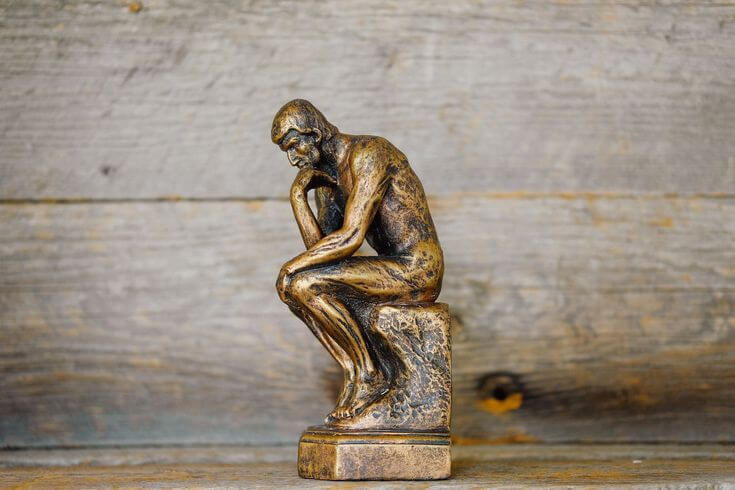
高市政権の高い支持率は、従来の政策では踏み込みづらかった領域に光を当てる起爆剤になっています。防衛装備品の輸出拡大は、防衛産業の強化や国際的な安全保障の枠組みへの貢献につながる可能性があります。特に、市場が自衛隊に限られてきた日本の防衛企業にとっては、販路拡大は存続の鍵とも言えるでしょう。
一方で、政治的リスクも無視できません。安保政策は国民の意見が割れやすく、野党との対立を激化させれば、物価高対策など国民生活に直結する政策が停滞するリスクがあります。また、支持率は「高く始まった政権ほど下落が早い」という過去の例が示すように、継続的な成果とバランスの取れた政策運営が不可欠です。
つまり、安保政策にアクセルを踏みつつも、国民生活に寄り添い、優先順位を見誤らない政権運営が求められています。
まとめ
高市政権は高い支持率を追い風に、これまで動かしづらかった安全保障分野の改革に踏み込もうとしています。防衛装備品の輸出制限の見直しは、日本の防衛産業成長や国際的役割を強化する可能性がある一方、政権運営には慎重な舵取りが必要です。
国民が最優先して求めているのは「物価高対策」である点を踏まえれば、安保政策の推進と生活課題への対応の両立が高市政権の成否を分けるポイントとなるでしょう。高支持率を「一時的な期待」で終わらせず、実績につなげられるかが、今後の政治の焦点となります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4db2ac24.61e0c2ad.4db2ac25.4b66e0fa/?me_id=1249489&item_id=10911293&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomicset%2Fcabinet%2F05139777%2Fbkbfuv5hej8ilobs.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=24419175&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3805%2F2000016943805.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント