今日は2025年8月31日の日経新聞電子版記事から、インフレと金利の関係に関する記事を取り上げたいと思います。

記事の要約
日銀と消費者の間で物価に対する認識のずれが広がっているというものです。
消費者としては日常生活で食品やサービスの値上げを強く実感している一方で、日銀は「これは一時的要因である」とみなして利上げを見送っています。
しかし実際は生鮮食品価格の高騰は気候変動の影響で長期化し、従来の物価指標では過小評価される懸念も指摘されています。
また、人手不足によるサービスの質が低下する実質的な値上げである「スキンプフレーション」も数値に表れにくく、消費者の実感と日銀の認識とのギャップをさらに広げる要因となっています。
記事に至る経緯

物価は経済活動の景況感に左右されるため「経済の体温計」といわれ、金融政策の判断に不可欠な存在です。
日銀は物価の動向を判断する上で、「基調的な物価上昇率」というワードを用いています。これは為替や天候などによる影響を一時的なものとみなして組み込まないことを意味しています。
結果的に、2%の物価上昇率を目標とするなかで、「現状の基調的な物価上昇率は1%台である」と判断し、1月以降は利上げを見送っている状況です。
しかし消費者物価指数(CPI)を見ると3年以上3%以上の上昇を続けており、生活者の実感と大きな乖離が生まれているのが実態です。
この背景には異常気象の頻発や人手不足があり、日銀のいう「一時的要因」として処理できない構造的な変化が進んでいることが挙げられます。
見解
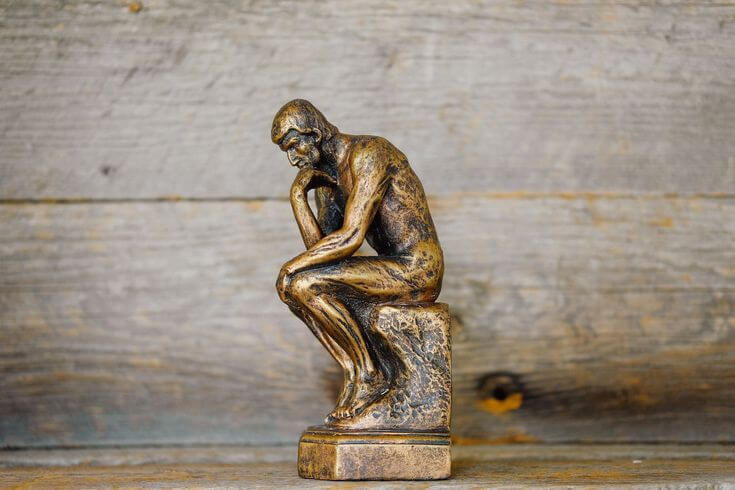
私はこの記事を読み、日銀の「古い物差し」での物価判断に限界が来ていると感じました。かつては一時的要因として切り捨てても問題なかった温暖化やグローバル供給網の変化も、今では慢性化しており軽視できない状況です。
また、「スキンプフレーション」は統計に表れにくく、消費者の負担感と政策判断の間に乖離を生んでいるのも問題です。
利上げの是非は単純ではないですし、利上げをして景気を冷やしすぎれば所得や雇用に悪影響が及びます。
しかし、生活者のインフレ体感を軽視し続ければ、政策への信頼は失われかねません。
今必要なのは、従来の指標に依存せず気候変動や人手不足といった新しい物価上昇要因を踏まえた分析と政策設計です。何よりもまずは消費者と目線を合わせることが求められていると感じました。
まとめ
消費者が「インフレ」と感じる現実と、日銀が「一時的」とみなす理屈の間に大きなギャップが生じています。このズレを放置していることで政策が後手に回っていることが指摘されており、今後かえって急激な対応を迫られるリスクが高まります。
物価を測る物差しを見直し、生活者のリアルな実感を政策判断に反映させることが、これからの日銀に求められる最大の課題だと考えます。
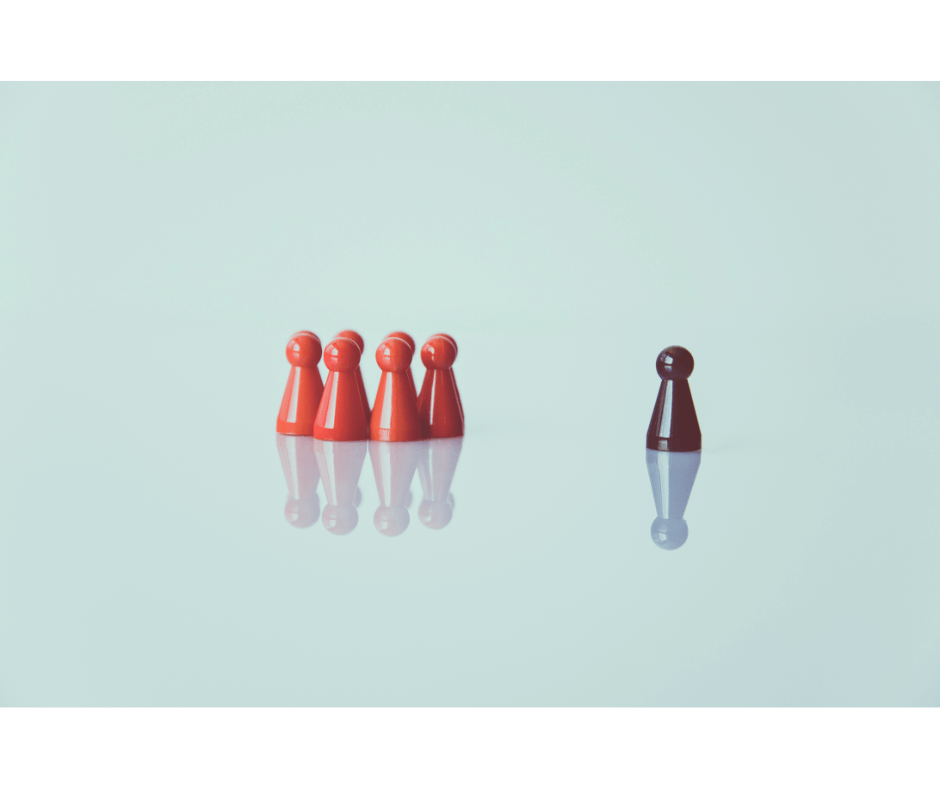
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=21593687&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1402%2F9784087861402_1_39.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


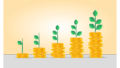
コメント