今日は2025年11月9日の日経電子版から、AIと雇用に関する記事を取り上げたいと思います。

記事の要約
生成AIを巡る国際競争が激化し、従来の企業経営の常識が大きく変わろうとしています。特に注目されているのが「AIエージェント」と呼ばれる新たな形のAIです。これは人間の指示を理解し、自ら計画を立ててタスクを実行する自律型ソフトウェアであり、2026年には本格的に普及期を迎えるとされています。
このAIエージェントは単なるチャットボットではなく、航空券の予約や資料作成、契約交渉などを自動でこなす存在です。世界の企業はAIを「労働力」として組み込み、AIと人間が同僚として働く未来を描き始めています。特に米国の企業では、人間とAIの協働による生産性の向上や新しいビジネスモデルの創出が進んでいます。
一方で、日本はAI開発・活用の面で遅れを取っており、今後は国としてどのようにAI社会に対応していくかが問われています。
記事に至る経緯

近年、ChatGPTやClaudeといった生成AIの進化が著しく、単なる「質問応答ツール」から「自律的に動くエージェント」へと発展しています。2025年には多くの企業がAIエージェント事業に参入し、「AIエージェント元年」と呼ばれるほどの盛り上がりを見せています。
特にソフトバンクグループの孫正義会長は「10億のAIエージェントをつくる」と宣言し、AIを新たな労働力として位置づけました。
また、エヌビディアやアマゾンなどの大手企業もAIによる業務効率化と雇用の再編を進めており、今後の企業構造や働き方に大きな変化をもたらすと見られています。
こうした世界的な潮流のなかで、日本のAI活用の遅れが浮き彫りとなり、国際的な競争力への懸念が高まっていることがこの記事の背景にあります。
見解
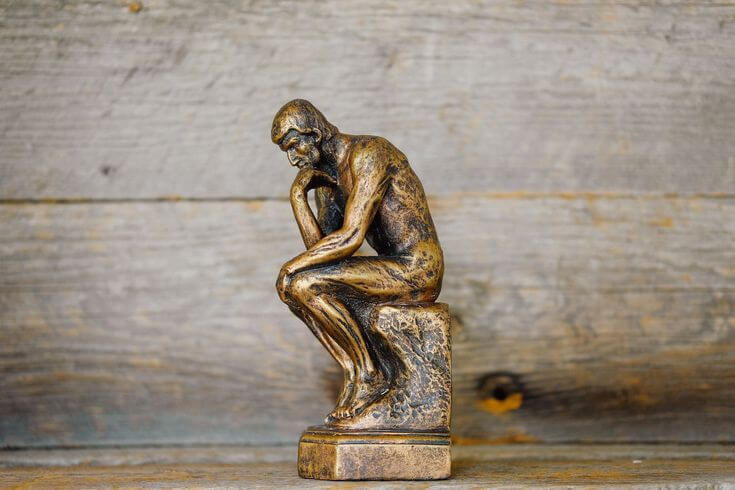
AIエージェントの登場は、企業経営だけでなく「労働の概念」そのものを変える出来事だと感じます。
AIが単なるツールではなく「同僚」や「チームメンバー」として働くようになれば、人間はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。一方で、単純作業やルーティンワークの多くがAIに置き換えられることは避けられず、雇用構造の変化も現実の問題として直面するでしょう。
そのため重要なのは、AIを排除するのではなく、「AIとどう共に働くか」を考える姿勢だと思います。AIの育成・監督・評価といった新しい職種が登場する可能性も高く、AI社会の中で人間の価値を再定義する時期に来ているといえます。
そして日本においては、技術開発の遅れよりも「AIに対する受け身の姿勢」が課題です。AIの安全性や倫理を重視することは重要ですが、世界の動きが加速するなかで、慎重さが停滞につながっては意味がありません。AIを正しく理解し、活用できる人材と環境づくりを早急に進めることが、これからの日本の競争力の鍵になると考えます。
まとめ
AIエージェントの普及は、これまでの働き方や企業経営の枠組みを根本から変える可能性を秘めています。
世界ではすでにAIを「新たな同僚」として迎え入れ、少数精鋭で巨大な価値を生み出す「スーパーカンパニー」が誕生しようとしています。
一方で、日本は依然としてAI活用に遅れをとっており、国としての存在感を示すためには、今こそ積極的な投資と人材育成が求められます。
AIとの共存を恐れるのではなく、AIを理解し使いこなす力を持つことが、次の時代を生き抜くための最大の武器になるでしょう。
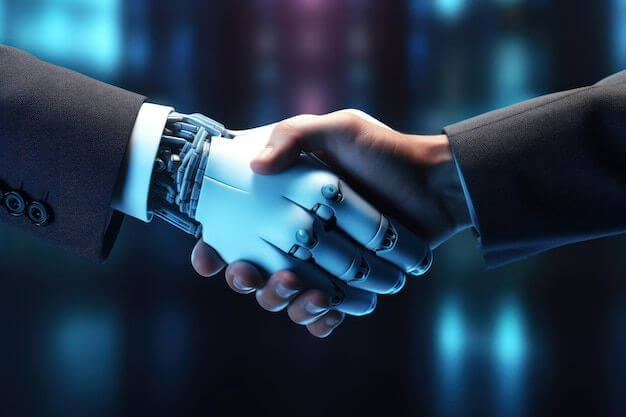
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=21742440&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8553%2F9784492558553_1_57.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=24043754&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4302%2F2000016244302.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント